A4用紙1ページで整理する「ブランド戦略」
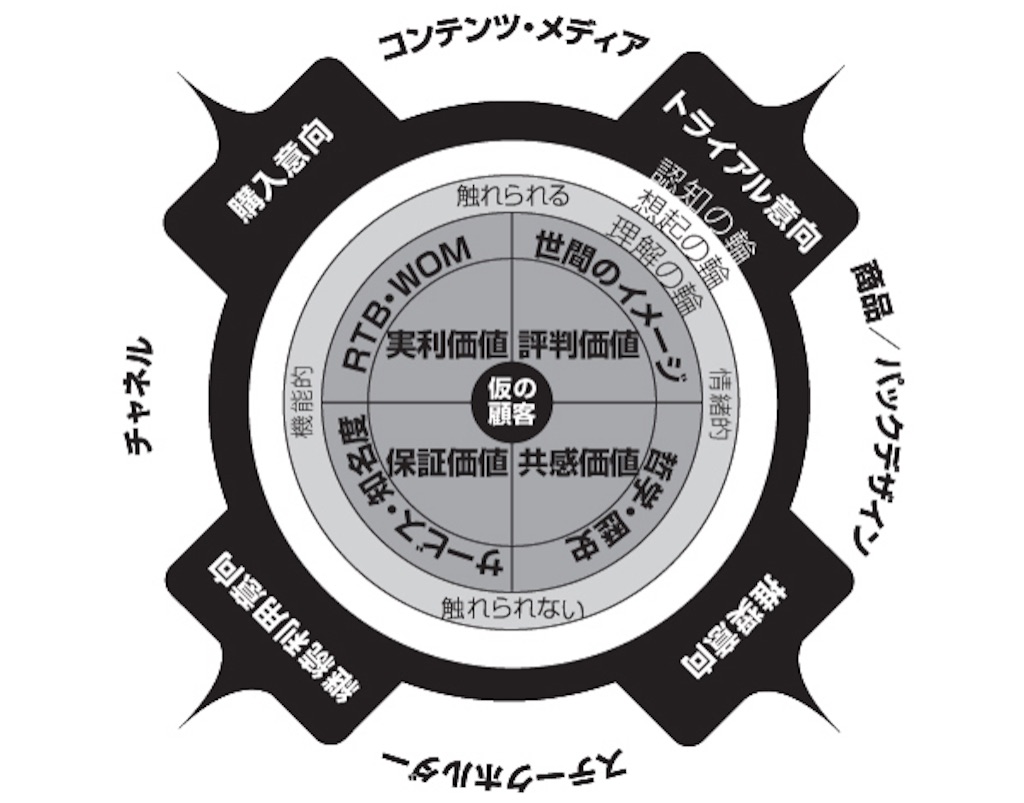
必要なのは、実は英語ではない――「グローバルな知性」を身につける4つの特効薬
グローバル企業で世界各国の優秀な人たちと接する傍ら、広告会社はじめ日本の名だたる有名企業の優秀な人たちともお仕事させていただく機会に恵まれ、「頭のいい人」「優秀な人」の定義が日本とグローバル企業ではだいぶ違うな、という印象を持つようになりました。
批判を恐れず乱暴に単純化してしまうと、日本では難しいことを理解できる人。グローバル企業では、どんなことでも簡単に単純に説明できる人。そんな 人たちが、それぞれ頭がいい、優秀である、と評価される傾向があるように思われます。これはどちらが良い・悪い、ということではありません。
グローバル企業では、偉くなればなるほど、非常にわかりやすい簡単な英語を話すようになります。日本でも、ヤフーの宮坂学社長のようにわかりやすく 事業や戦略を語る能力は、マネージメントとして大きなアドバンテージではありますが、偉くなればなるほど話がわかりやすくなる、という一貫した方向性が見 られるわけではありません。
グローバル企業には、あらゆる国や地域から様々な文化が持ち寄られているので、文化的なコンテクストに依存しない、誤解の生じ得ない平板な表現が重んじられるのは自然なことです。
しかし、ビジネスの世界は、そう単純ではありません。それどころか、多様化する価値観やグローバル化の進展により、その複雑さは増す一方です。世界経済フォーラム(World Economic Forum)が発表した、「The future of jobs:仕事の未来」によると、2020年に重視されるスキルベスト10の第1位は「複雑な問題を解決する能力」です。だとすると、グローバル企業のリーダーたちは、いかにしてそれを単純化して理解し、伝えているのでしょうか。
Insight(インサイト:洞察)という言葉があります。グローバルなビジネスの現場では頻出の単語です。数学の証明問題で、補助線というのが あったと思います。検討もつかなかった問題の解が、一本の補助線をひくことによって、まるで魔法のようにつまびらかになっていく。インサイトとは、ここで いう「補助線」になるような、複雑な現実をわかりやすくスライスする視点です。
例えば、「〇〇的な」という若者の言葉遣いに対して、何年くらいから使われはじめたのか、特定の起源はあるのか、あるとしたら誰なのか、起源から現 在までに使われ方の変遷はあるのか、文法的にどこが妥当でどこがそうじゃないのかなど、あらゆる軸で検討し、それを「マトリックス」で整理するのが日本型 の知性です。それゆえ、日本の広告会社のストプラ(ストラテジック・プランナー)の方の提案にはマトリックスが非常に多いように思われます。
一方、「〇〇派の時代から〇〇族の時代を経て、〇〇系から〇〇的に至る過程で、グループは多様化し、相互の対立はどんどん緩やかになってきた。〇〇 的はその意味で現代的な集団意識」などという視点で、事象をシンプルに整理するのがインサイトです。このような考え方を「インサイトフル」などといったり します。
続きはアドタイでご覧ください
必要なのは、実は英語ではない――「グローバルな知性」を身につける4つの特効薬 | AdverTimes(アドタイ) - Part 2
国家プロジェクトをもかき回す「ロゴ」という偶像、「ブランド」という念仏
コンサル会社の広告界への参入」が日本で意味すること
「憲法」という言葉の誤訳から、意識高い系の横文字多様を擁護する
テレビで「憲法はなぜ必要か?」という特集をしていて非常に驚きました。憲法の重要性を解りやすく伝える、という制作者の趣旨は解るものの、ぱっと聞いた感じ非常に突飛な印象を受けます。憲法は国の設計図なので、憲法がなぜ必要か?というのは、国はなぜ必要か?という問いと同じです。護憲か改憲か、というレイアーの話ではなく、言葉の定義の問題です。例えば極端な話、たとえ無政府主義者であっても、国家を樹立した際にはそもそもその「政府は不要」という国のあり方が憲法に規定されるが故、憲法は尊重することになります。専制君主に絶対的な統治権があり、その統治権は全ての法律に優先する、というのも、近代的な立憲主義の精神には悖りますが、一つの国の設計図といえます。憲法は明文化されている場合とそうでない場合がありますが、憲法の数だけ国家がある、と考えることもできます。アメリカ合衆国は連邦国家(邦=国)なので、それぞれの州(stateというのは文脈によっては国とも訳します)が独自の憲法を持つ国家です。それゆえ、州によって同性婚が可能だったり不可能だったり、マリファナが合法だったり非合法だったりするのです。国の設計図である憲法が違うためです。

英語のConstitution(憲法)には、civil law(民法)とかcommercial law(商法)とかcriminal law(刑法)のようにlaw(法律)という言葉はついていないのに、それを明治時代に憲「法」と訳したのがそもそもの間違いの始まりです。この憲法という言葉自体は、聖徳太子の「十七条の憲法」を例に出せば解りやすいですが、本邦では古来から使われてきたものです。ただ、例えば日本書紀に出てくる憲法(いつくしきののり)という言葉は、本来は官吏が従うべき論理的な規範を定めたもので、役所の省内の決まり事のようなものであり、constitutionの本来の意味である「国家の設計図」ではまったくありません。官吏(公務員や国会議員)を縛る、という表面的な類似性こそありますが、概念としてはまったく別々のものです。例えて言うなれば、constitutionは家を建てるときに建築家が書いた設計図です。十七条の憲法などにいう「憲法(いつくしきののり)」は、「現場では必ずヘルメットを着用する」「タバコは所定の喫煙スペースで」などというルールに近いものです。ともに現場で作業をする大工たちを縛る決まり事ですが、本質はまったく異なります。
つまり、憲法という日本語は、当時の時点では誤訳です。言葉の意味・定義というのは生き物で、時代とともに一般的な用法・用例が変化するに従い変遷していくので、今日の「憲法」という言葉の辞書的な定義には、近代的な意味での憲法、国の設計図という概念も含まれています。しかし、辞書というのは、公文書から学術文書、市井の会話の記録を含め様々な資料をあたって用法用例を分析して編纂するものです。一般人が公文書上、学術文書上の用例を把握していることは少ないですし、この正しい定義で憲法という言葉を理解できている人は少ないのではないでしょうか。だからこそ冒頭の「憲法はなぜ必要なのか?」などというテレビ番組が成立し得るのです。多くの人は古来使われている「憲法」という言葉の意味など知る由もありませんが、それでもこの翻訳はやはり不適切です。「法」という言葉が入っていることで、ある種の法律なのだろう、法律の親分みたいなものだろう、という誤解を生んでしまいますし、「十七条の憲法」などという用例と区別できないのでそこでも誤解が助長されます。これらの誤解は、多少大げさに響きますが、立憲主義という現代的な国家のあり方に対する誤解にもつながっていると考えます。
明治維新を幕開けに外国文化が大量に流れ込んできた際、明治の知識人たちは、いくつもの「日本語にはない」概念を苦心して翻訳してきました。この「概念(concept)」という言葉にしたってそうです。文化的な文脈を完全に訳出することはできないので、どんな言葉の翻訳も誤謬はつきものです。ただLost in translationで意味が抜け落ちてしまっていたり、「現存在と存在者」のようにそれだけでは全く意味不明であったりすればまだよいですが、間違った理解を助長するのであればそれは誤訳であり有害です。それならなお、憲法はそのまま、コンスティテューションとカタカナで言っておけばよかったのではないでしょうか。私自身、かつて若い方に「それはマーケティグとITをグロスした視点ですね」と発言を要約いただいた際非常に狼狽したクチではありますが、うまく訳出できない場合は横文字をそのまま使う、というスタンスは上記の理由から支持します。